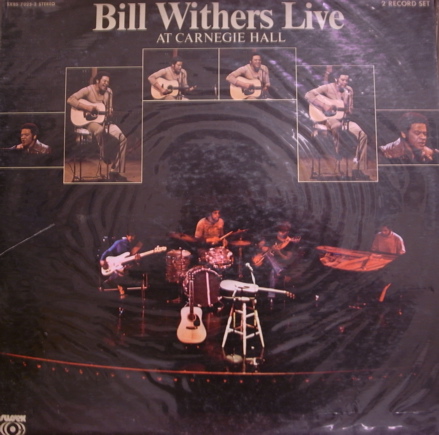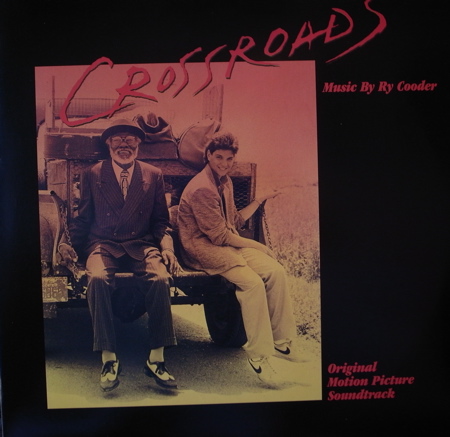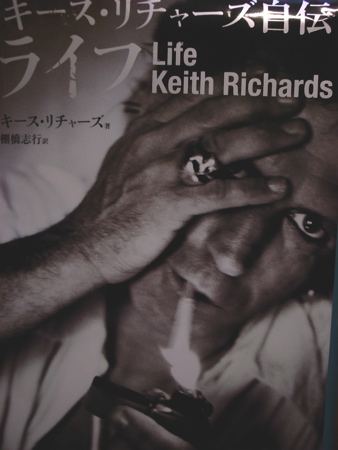『ザ・コジモ・マタッサ・ストーリー』(PROPER BOX 129)
1950年代、ニューオリンズからいくつものR&B,R&Rの名曲が生み出されたが、その生みの親のひとりが当時ニューオリンズでスタジオを経営し、エンジニアでもあったコジモ・マタッサ。そのコジモが録音した数々のヒット曲、名曲をコンピレーションしたアルバム4枚組。
その曲目とミュージシャン名を見ただけで「いゃ〜、すごいなぁ」とため息が出た。
音楽があふれるニューオリンズで生まれ育ったコジモは、大学をドロップ・アウトしてブラブラしていたところ父親から「働くか軍隊に行け」と言われて、ジュークボックスやレコードを販売する仕事を始める。当時、ニューオリンズにはレコーディング・スタジオがなく、素晴らしいミュージシャンがたくさんいるのにみんなよその街にレコーディングに行っていた。そこで音楽になかなかいい耳をもっていたコジモは、「儲かるんとちゃうか」とスタジオを経営し始める。
その名がJ&Mスタジオ。最初はぱっとしなかったけれど、ロイ・ブラウンというブルーズ・シンガーがJ&Mで録音した"Good Rockin' Tonight"(タイトルが最高!)が1947年に大ヒットして、次第にスタジオの名前が知られていく。
その後、ファッツ・ドミノ、ロイド・ブライス、ギター・スリムなどJ&Mで録音したミュージシャンが次々にヒットを出して、50年代半ばにリトル・リチャードが放った数々のR&RによってニューオリンズのJ&Mスタジオとエンジニアのゴシモ・マタッサの名前は決定的に知られることになる。そして、インペリアル、アトランティック、スペシャルティなど全米のレコード会社がJ&Mスタジオでの録音を求めて来た。
この初中期にニューオリンズ・サウンドのプロデューサーとして腕をふるい、ミュージシャンとレコード会社の間に立って交渉もしたのがディヴ・バーソロミュー(のちにその役割を受け継いだのが現在もニューオリンズのプロデューサーとして活躍しているアラン・トゥーサン)。
50年代のニューオリンズ・サウンドの栄光というのは、コジモ・マタッサ(エンジニア)+ディヴ・バーソロミュー(プロデューサー)のふたりと、アール・パーマー、リー・アレン、フランク・フィールズなどニューオリンズの優れたミュージシャンたちによって作られていった。
J&Mはのちに移転してコジモ・スタジオと名前を変えたが、コジモはレコーディングに関して創意工夫し、R&BやR&Rの斬新なサウンドの誕生に大きな功績を残し、その名前は海を越えて海外にまで知られるようになった。
コジモは業界から引退したもののまだ健在で、このアルバムのブックレットにも好々爺となった彼の最近の写真が収められている。
このコジモからヒットを出して世に出たミュージシャンの名前をざっと挙げてみよう。ファッツ・ドミノ、ギター・スリム、リトル・リチャード、シャリー&リー、ロイド・プライス、スマイリー・ルイス、プロフェッサー・ロングヘア、アール・キング、アート・ネヴィル・・・と、歴史に名前の残るミュージシャンばかりだ。
新しい音楽が生まれ、育っていく輝かしい録音の日々がこの4枚に収められている。
そして、製作するお金だけではなく、ミュージシャンとプロデューサーとレコーディング・エンジニアの才能と努力と工夫なくして名曲は生まれないし、ヒットもしないという見本のような『ザ・コジモ・マタッサ・ストーリー』でした。お薦めのコンピレーションです。プレゼントしてくれたニューオリンズの山岸潤史に感謝。
ジャケット写真とコジモさんの写真と、もうひとつなぜかリトル・リチャードがブランコに乗ってる写真(やはりおネエ系のムードがどことなく漂ったイカシた1枚)です。