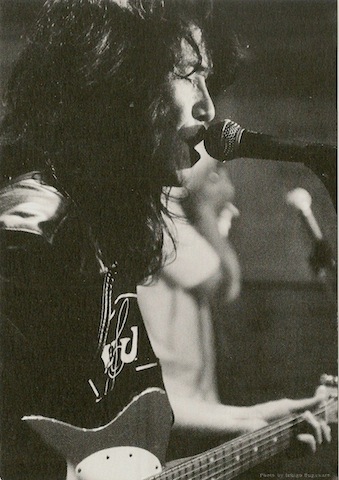僕は最近のディランを増々好きになっている。最近、一部で『カエルを押しつぶしたような声』と揶揄されている歌声だが何十年と歌い続ければ歌声は変っていくし、『カエルを押しつぶしたような声』というならそれは信じられないくらい巨大なカエルだろう。僕にとっては暖かみもあるし、切れもある「いい声」だ。とくに低い声は魅力的だ。気持ちが高ぶっていたのか早めだったが会場に向かった。
大崎から乗った電車の前の席に座っていたのは、若き日のディランのようなもじゃもじゃ頭の20代後半くらいのバンドやってそうな男とその横には美しい長い黒髪の女性。ジョーン・バエズのようにきれいだった。「このふたりは絶対ディランに行くな」とテレポートの駅からふたりの後をつけていったらやっぱり会場に着いた。
ハイボールを2杯飲んでちょっといい気分になったところで客電が消えた。
仄暗いステージに現れたディランとメンバーたちは、デヴィッド・リンチの映画のワンシーンのようだ。あの「ブルーヴェルベット」のような。
1曲目が始まった時からとにかく音が、音響がすごくいい。スチュ・キンボールのアコースティック・ギターの音も、ジョージ・リセリのブラシの切れも、ディランの歌の繊細な表現も実に見事に聴こえてくる。
たぶん、会場の大きさもこのくらいまでがいいのだろう。「音楽」をちゃんと聴く広さだ。
音楽の質の違いもあるが先日のドームのストーンズの音はスタンドにいた僕の位置ではあまりいいものではなかった。
まあ、ストーンズはお祭り的な楽しさの方が大きいバンドだから・・・とは思うが、やはり一度もっと小さい会場で、ストーンズの「音楽」を堪能できる会場で聴いてみたい。
曲は60年代の"She Belongs to Me"や大好きな"Tangled Up in Blue","Love Sick"もあったが、比較的新しい、最近の曲が多くとくに"Tempest"からの曲が多かったように思う。ディランの音楽にはフォーク、スピリチュアル、R&R、カントリーからポップまで、早く言えばアメリカ大衆音楽のすべてが入り込んでいるが、前回と同じように全体的にブルーズのテイストを感じさせる重厚なものだった。それにしても"Like A Rolling Stone"や"Just Like A Woman"などよく知られている昔の曲は本編では一切やらなかった。アンコールでやった2曲"All Along the Watchtower""Blowin in the wind"だけだ。本当に「おまけ」な感じだった。
ディランの表情までは会場一階の真ん中あたりにいた僕のところからでは詳細には見えない。衣装はみんな同じではないが、同じようなテイストで作られていて誰ひとり着せられている感がない。クールだ。ステージのムードもすごいいい。やたら派手な照明をするだけが良いというものではないことを見せてくれた。とにかくチャラチャラ感は一切ない。けど威圧感もない。すべてが必要最小限でありながら洒落ていて、ムードは寡黙だ。
途中で休憩をはさみながら2ステージ。2時間と少しのステージでMCは「15分休憩する」と言っただけだった。メンバー紹介もなかった。黙々と曲を続けた。メンバーの演奏は余計なことは一切なく、誰が目立つわけでもなく、長いソロもなく前回より更にバンド感が増していた。そして、ひしひしと押し寄せるグルーヴの波。もう、ジョージ・リセリとトニー・ガーニエ、スチュ・キンボールを中心に作られるグルーヴはあまりにも見事でずっと聴いていたいほどだった。チャーリー・セクストンが時折弾く短いソロやオブリガードも気が利いている。そして、演奏に彩りをくわえるドニー・ヘロンのバンジョーやマンドリンなどの美しい音色。
そして、ディランだ。72才。偉大な人だが、ただ単に音楽が好きで好きで、ライヴが好きで好きでやり続けているひとりのミュージシャンと見える。ほとんど表情も変らないし、取り立ててアクションするわけでもなく、MCもない。でも、ディランは『ほら、楽しいよ。音楽は本当に楽しいよ。ずっとライヴやるのは楽しいよ』と言っているようだった。
時折、"Soon After Midnight"や"Long and Wasted Years"のような胸をしめつけるメロディを、何十年と音楽に捧げられた素晴らしい声で歌われると何故か漠然と自分が生きてこの場所にいることにすごく幸せを感じて落涙しそうになる。
最後、アンコールが終わってステージ前に揃ったメンバーたちは笑うでもなく、肩を組むでもなく、おじぎをするでもなく、客席を見つめひとつも表情を変えないままだった。そして照明が消えた。そのあっ気なさがたまらなかった。
またしてもディランにやられてしまった夜だった。