 |
||
 |
||
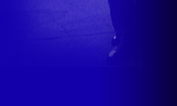 |
||


| MY NOTES > My Feeling For The Blues > No.14 |
| The Blues Movie Project その5 |
| ゴッドファーザーズ&サンズ/Godfathers & Sons マーク・レヴィン監督 |
| 監督のマーク・レヴィンは、カンヌ国際映画祭でカメラ・ドールを授賞した『SLAM』という映画で評判になった人らしいが、私はまだそれを観ていない。今回の映画のタイトルについては、監督自身が1969年のマディ・ウォーターズのアルバム「ファーザーズ&サンズ」から取ったと言っているのでまず、そのアルバムについて触れてみたい。 「ファーザーズ&サンズ」(ジャケット写真Photographにあり)私はこのアルバムを71年頃に手に入れた。もちろんアナログ・レコードで。CDになってからは1枚だが、レコードは2枚組になっていて1枚はスタジオ録音、もう1枚はライヴ録音だ。タイトルのファーザーズ(お父さんたち)とは50年代シカゴ・エレクトリック・ブルーズの創始者、マディ・ウォーターズとその右腕のピアノのオーティス・スパンのことを指し、サンズ(子供たち)とは白人のブルーズマン、ポール・バターフィールドとマイク・ブルームフィールドたちのことを意味している。 私はこのアルバムを死ぬほど聴いた。聴いて聴いて聴きまくった。当時、ロックからブルーズにシフト・チェンジしつつあった私の胸を最も熱くさせたのが、このアルバムだった。マディの圧倒的な声の存在感とそれを取り巻くサウンドの厚さ、新しさ、そして、随所に感じられるブルームフィールドのギターによるロック・テイストなども私を夢中にさせた要因だった。バターフィールドのパワフルなハープやブルームフィールドの熱のあるギターに、マディは触発され5.6才は若いプレイをしている。とくにライヴのスライド・ギターのエグさはいま聴いても強烈なものがあるし、"Mojo Workin'"のグイグイとくるノリにも興奮してしまう。ブルーズを歌い、プレイしょうとする者には必聴の1枚! 私はこのアルバムから50年代のマディへ、そして同じチェス・レコードのハウリン・ウルフ、サニーボーイへと一挙に遡った。あとはもうマディ・ウォーターの洪水、ブルーズの泥沼だった。 「チェス・レコード」 シカゴの「チェス・レコード」は50年代から60年代にかけて優れたブルーズ、R&Bのレコードを数多くリリースした会社だ。所属したブルーズマンをざっと挙げてみよう-マディ・ウォーターズ、ハウリン・ウルフ、サニーボーイ・ウィリアムスン、リトル・ウォルター、J.Bルノアー、ジミー・ロジャース、バディ・ガイ・・・・・そして、ロックンロールのジャンルではチャック・ベリーとボ・ディドリー、R&Bのレーベル「チェス・チエッカー」からはリトル・ミルトン、エタ・ジェイムズなどまさに50-60年代の黒人音楽の宝庫だ。そして、この会社を立ち上げたのが、この映画でよく喋っているマーシャル・チェスの父レナードと叔父のフィルだ。ふたりはポーランドからの移民だが、当時シカゴにはヨーロッパ人やユダヤ人の移民がたくさんいて、貧しい彼等は黒人と同じような地域に住んでいたために黒人の音楽を商売にすることを考えついたようだ。チェス・レコードの根幹は叔父フィルと父レナードの力によって作られ発展した。そして60年代後半からマーシャルが引き継いだが会社を存続、拡大することはできず69年に売却された。いろいろと喋ってくれているマ−シャルだが、ビジネスよりも遊びの方でストーンズに係わっていた放蕩息子というイメージが私には強い。 それはともかく、チェスが残した音源はいままでも何度も繰り返し発売されてきたことが証明するように本当に素晴らしいものだ。ブルーズ・ビギナーの方はマディやウルフ、サニーボーイあたりからゆっくりとチェス・ブルーズ巡りをされたらいいと思う。さて、そのチェス・レコードの末期、68年に作られたのが「エレクトリック・マッド」というアルバムだ。 「エレクトリック・マッド」(ジャケット写真Photographにあり) 68年と言えば、ビートルズの「マジカル・ミステリー・ツアー」が発表され、クリームは解散し、ザ・バンドがデビューし、ラジオからはオーティス・レディングの「ドック・オブ・ザ・ベイ」が流れ、それを聴きながら私は受験勉強を嫌々やっていた。 前年にビートルズの「サージェント・ペパーズ・・・」が発表され、ジミ・ヘンドリックス、ドアーズなどがデビューし、サンフランシスコあたりから「サイケデリック・ロック」というエフェクターを多用したロックが流行り始めていた。その年に録音された「エレクトリック・マッド」は、自社の看板歌手であるマディをファンク・ロック・ビートとサイケデリック・サウンドに包み、白人ロック・ファン層相手に売ろうとマーシャル・チェスが画策したアルバムだった。実際、マディのアルバム、そしてブルーズのアルバムとしてはかなりのセールスだったという。しかし、このアルバムは一部のブルーズ・フリーク、評論家には最悪のアルバムと酷評されることとなった。セールスが上がっていた50年代に比べると、明らかにレコード売り上げが落ち込んでいたマディがどんな気持ちでこのアルバムの録音を行ったのか?もちろん、マーシャル・チェスは「マディ、いまの時流のサウンドはこれなんだ。これに乗って新しい白人の若い層をファンに取り込んで、売っていこうじゃないか!」と、アルバム・コンセプトを説明したことだろう。私が知っているこのアルバムに関するマディの発言は「アルバムが売れたのはいいけど、あのサウンドをライヴ・ステージで再現できなくて、白人の若い客にあのサウンドを要求されると困ったよ」だけだ。つまり、マディの普段のバンドサウンドはアルバムのようなものではなく、あくまでも50年代に出したヒット・サウンドの延長線上にあるものだった。ワウワウはじめエフェクターを多用したものではなく、フリージャズっぽいソロも16ビートもないものだった。そして、このアルバム製作後、マディのバンドサウンドが変化し、このアルバムのようになることはなかった。そこから察するとマディはこのアルバムのサウンドがそんなに好きではなかったと推測できる。このアルバムが売れたからと言ってマディには自分のサウンドを急激に変化させる気持ちはなかったし、恐らく彼は自分のブルーズが自分らしく表現できるサウンドはこれではなく、いままでのサウンドの方がよいと判断したのだ。だから、映画の中でマ−シャルが自慢気に「このサウンドにマディも満足していた」と発言しているのは、私には眉唾ものだ。 では、このアルバムがつまらない代物かと言えば、そうではない。今回、このアルバムを久しぶりに聴き返してみてまず思ったのは、どんなにワウワウが鳴ろうが、ドラムがドカドカやろうが、サックスがフリージャズしょうが、真中にいるマディは毅然として変わらず堂々とした存在感を示していることだ。マディは偉大だ。私も歌手の端くれだから一言言わせてもらうなら、いままで歌ってきた歌のビートを変えられるというのはなかなかツライものだ。このアルバムの中で歌われている "I Just Wanna Make Love To You""I'm Your Hoochie Coochie Man"などのマディのヒットは元々シャッフル・ビートだ。その長年シャッフルで歌ってきた曲を16ビートにアレンジされたマディはたぶん戸惑ったことだろう。少なくとも普段16ビートの曲を歌っているならまだしも、マディのレパートリーにその手の曲はない。つまり、彼の身体の中には16ビートがセットされていないのだ。そういうマディにとって、こういうアレンジで歌わされるのはかなりつらいものがあったのではないかと推測する。実際、よ〜く聴くとシャッフルのりの名残りがあるところもあるが、その強力な声だけですべてはふっ飛んでいる。また、サウンドのかなり前面に出てきているパワフルなドラム(モーリス・ジェニング)とベース(ルイス・スターフィールド)のグルーヴにグイグイと引っ張っていかれるのは気持ちいい。このリズム隊もマディの後で、そしてソロでワッカ、ワッカ、ム〜〜ン、ム〜〜ン、ミ〜ン、ミ〜ンと唸っているピ−ト・コ−ジのギターも、1曲目の"I Just Wanna Make Love To You"で終りなのになかなか終らないオルガンの突っ走り加減も、私には笑える。結局、全曲「バンドは大騒ぎ!お祭り騒ぎ!」だ。もうひとりのギタリスト、私の大好きなフィル・アップチャーチなど腕達者なメンバーが担ぐお神輿にニャッと笑いながら、そして時折「オイオイ、そんなに揺らすと落ちるじゃないか!」と言いながら、満更でもなくのっているマディ御大といった風だ。 マディのアルバムの中では確かに異色であり、頭のカチカチなブルース・ファンがこのアルバムを嫌う気持ちもわからないでもないし、マディにはもっと素晴らしいアルバムがあることも事実だ。でも、マディの「この時流のサウンドにノってやろうじゃないか!」という気概が私には伝わってくるし、そこには嫌なことをやらされているという悲惨な感じはない。自分の音楽として満足はしなかったが、このレコーディング・セッションを結構楽しんだように思える。天国で自分のたくさんアルバムを振り返りながら「おもろいやろ、これ。ちょっと聴いてみるか・・はははははは。笑えるやろ。」と言ってるような気がする。 「ゴッドファーザーズ&サンズ」 今回の映画「ゴッドファーザーズ&サンズ」はその「エレクトリック・マッド」の中の「マニッシュ・ボ−イ」の音源を使って、オリジナル・レコーディング・ミュージシャンだったピート・コージ、フィル・アップチャーチなどが、ヒップホップのチャックDとコモンとコラボレイトする話だ。つまり、今回はピート・コージー、アップチャーチたちがファーザーズでチャックDとコモンがサンズというわけだ。そして、ゴッドファーザーズとはマディのことだろう。そして、これをプロデュースするのが昔プロデュースしたマーシャル・チェス。68年のオリジナル・アルバムには彼の他にサックスのジーン・バージとオルガンの亡きチャールズ・ステップニーの名前が入っているが、実質的にサウンド・プロデュースをしたのはこのふたりだろう。 マディの声を使ってピート・コージー、アップチャーチたちがサウンドを再構築した後に、チャックDとコモンたちのヒップホップ連中がラップやスクラッチを入れ込むという録音風景が映し出されていく。私もかって自分のアルバム「Fool's Paradise」でオリジナルのブルーズ・ラップを作ったことがあるので、このプロセスはとても興味深いシーンだったし、この映画でもっとも興奮した場面だった。この曲はこの映画シリーズの関連CD「マーティン・スコセッシ・プレゼンツ・ザ・ブルーズ/ゴッドファーザーズ・アンド・サンズ」(Hip-O B0000627-02)で聴くことができるが、なかなかおもろい出来上がりだと思う。 映画の中でチャックDやマーシャル・チェスが盛んに現在のヒップホップのルーツであるブルーズを若いもんは聴くべきだと語っているが、まあこれを聴いたからと言ってみんながブルーズに耳を向けてくれるとは思わない。日本でも、そういうことをブルーズの流れている飲み屋で若い奴に説教しているおっさんを時々見かけるが、説教すればするほど離れていくのになぁ・・・と私は思っている。なぜなら私は音楽について説教されるのが大嫌いだからだ。音楽の嗜好は人によって千差万別だから・・・。しかし、こういうブルーズ関連の映像や音楽を若い人たちの前に提供する、ポピュラーな場所に提供することはすごく大切で、今回のこの一連の映画公開に私も微力ながらお手伝いさせてもらったのはそういう気持ちからだ。そして、たくさんの人がブルーズを耳にし、そこからまた新しい音楽が生まれてくれることを私も願っているし、自分でも新しい試みをすることを恐れてはいけないと思っている。 映画はもちろん、それだけでなくオーティス・ラッシュやアイク・ターナーとパイントップ・パーキンスがピアノを連弾するシカゴ・ブルーズ・フェスティバルの映像、そしてハウリン・ウルフやポール・バターフィールド・ブルーズバンドなどの過去のお宝映像も随所に登場する。また、冒頭に登場するココ・テイラーの映像にはシカゴのブルーズ・シーンで活躍する菊田俊介君の姿も映っている。チェス・レコードのコレクションはほんとに素晴らしいアルバムにあふれています。みなさんも少しづつその本物のブルーズに触れてみてください。まずは「ベスト・オブ・マディ・ウォーターズ」あたりからどうぞ。 |
|
| Page Top |