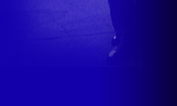監督のチャールズ・バーネットはアイス・キューブが出演した「グラス・シールド」という映画を製作した人だということだが、私は残念ながら観ていない。この「デビルズ・ファイヤー」は監督自身の子供の頃の体験も多分に含まれているらしいが、都会に住む黒人の男の子が洗礼を受けるためにニューオリンズのおじさんを訪ねてくるのだが、おじさんは教会よりも酒場の方が好きな、しかも大いに女に興味のある「ワルイ」人。そして、おじさんは自分の女の家や酒場などにこの甥っ子を連れ回しながら、ブルーズや黒人たちが生きて来た歴史を語るという話だ。この"The
Blues Movie Project"シリーズの7本の中では、このフイルムがいちばんドラマ仕立ての作品になっている。
映画は甥っ子がニューオリンズの駅に着くところから始まるが、昔(何年代かはちょっとわからないが)の実写のフィルムからうまくこの映画のフィルムに移っていく。教会に行きたがる甥に向かっておじさんは「天国に行くために大人しくしていて何になる。人生は一度きりだぞ」と言う。その言葉には私も「賛成!」。そして、おじさんの家に行ったり、彼の友人や女に会ったりする生活を共に体験しながら進行していくドラマの中、サン・ハウスやシスター・ロゼッタ・サープ(レッド・ホワイト&ブルーズに出てきたフィルムとはまた違うもの)、メイミー・スミス(ブルーズを初めてレコーディングしたといわれる女性シンガー)アイダ・コックスなどブルーズマン、ウーマンの昔の貴重なフィルムが挟まれる。しかし、この映画の前半、私にとって最も嬉しかったのは年代やバック・ミュージシャンはわからないが、40年代から60年代にかけて活躍したジャズ、ブルーズの女性歌手ダイナ・ワシントンの実写が現れることだ。ほとんど1曲まるごと歌っている姿が映る。歌っている"I
Don't Hurt Anymore"から推測すると50年代の終り頃ではないかと思う。その堂々とした立派な歌いっぷりは、さすがヒットを連発し一時代を築いた大歌手だけのことはある。また私の好きなエスター・フィリップスが憧れたダイナの姿は、こういうものだったのだろうと感慨深いものがあった。
その後にはサニーボーイ・ウィリアムスンの以前から出回っているヨーロッパでのフィルムや、去年から今年にかけてDVDで発売されブルーズ・フリークが皆「生きててよかった」と言う"American
Folk Blues Festival"からのマディ・ウォーターズやT.ボーン・ウォーカーのフイルムも出てくる。"American Folk
Blues Festival"からは他にもウィリーディクソン、ヴィクトリア・スパイヴィーの姿も登場する。そして、中盤で最も印象に残るのはストリートで演奏するライトニン・ホプキンスのいなせな姿だ。その後にはすでに有名なフィルムとして知られている、映画に出ている「ブルーズの女王」ベッシー・スミスが登場する。後半の実写フィルムのハイライトはひとりで椅子に座りヒット曲の"Boom
Boom"とスロー・ブルーズを歌い、弾くジョン・リー・フッカーだ。そのタフで、ラフなふてぶてしい姿が、まさにブルーズマン、ジョン・リーを感じさせる存在感たっぷりの映像だ。そのプレイはもちろんブルーズであり、しかもファンクであり、パンクであり、ロックだ。これを観てホレない男はブルーズ・フリークの男じゃない?!・・と、やや精神的ホモな気分にさえなる。また、映画全般にちりばめられている過去の黒人たちの生活の様子を映した実写は、ブルーズだけでなくゴスペルなど黒人音楽を理解する上での助けになっている。そのあたりも見逃さずに注意して観てください。まあ、映画のストーリーは他愛ないものだが、随所に挿入されているそういう実写フィルムや写真、テロップで流れる言葉などの奥には深い意味が流れている。
タイトルの"Warming By The Devil's Fire"は「悪魔の火にはあたらない」つまり、「悪魔の焚く火にあたって暖まってはいけない」という聖書の言葉から来ているらしい。ブル−ズは悪魔の音楽だからそんなものにのめり込んではいけないということなのだろうが、この映画のおじさん同様に私もずっと悪魔の火のそばで身体を暖め、その火をいろんなところにバラまいた悪魔の手先のひとりである。 |