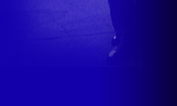60〜70年代のソウル・レーベルと言えばデトロイトの「モータウン・レコード」とメンフィスの「スタックス・レコード」がその代表的なものだった。
僕がラジオでヒット・チャートを追いかけていた中高校生の頃(60年代)、ビートルズはじめ華々しいブリティッシュ勢の活躍の合間に耳にするのはキュートな歌声のシュプリームスはじめモータウン・ソウルの方が多かった。スタックスと比べるとやはり断然モータウンの方が音作りがポップで一般には受け入れられやすいからだろう。それはそれで楽しいしいまでもモータウン初期のミラクルズやテンプテーションズ、シュプリームス、メリー・ウェルズ、マーサ・リーヴス&ザ・ヴァンデラス、タミー・テリルとマーヴィンのデュオなどを聴いては一緒に歌ったりしている。
でも、20才を過ぎて自分が音楽をやることに熱中してからは「スタックス」の方がより身近なレーベルとなった。たぶん、それはスタックスの方がブルーズのテイストが濃かったからだろう。実際、スタックスはアルバート・キング、ジョニー・テイラー、リトル・ミルトンなど優れたブルーズマンを擁していたし、ステイプル・シンガーズ、ソウル・チルドレンのようなゴスペルに直結しているアーシーなグループも多かった。しかし、何と言っても最初のお気に入りはオーティス・レデイングだった。いま聴いてもオーティスの火の玉のような熱いソウルには自分の魂も熱くなってしまうし、シンガーとして自分の姿勢を正される思いがする。そして、サム&デイヴだ。このソウル・デュオが最もソウル・デュオと呼ぶのにふさわしいのではないだろうか。ソウル・ミュージックをまだそんなに知らない頃から、オーティスやサム&デイヴの歌声には魂からあふれ出てくる切迫したフィーリングを感じていた。そして、その止めがたい感情(ソウル)を求めて私はスタックスからサザン・ソウルという広く深い歌の世界に入り込んで行った。スペンサー・ウィギンス、ボビー・パウエル、ジェイムズ・カー、デッド・テイラー・・・と一時はシングル盤を追い求めるところまで行ったが、とどめを刺されたのはO.V.ライトだった。いまでも一番好きなソウル・シンガーはO.V.ライトで揺らぐ事はない。
そういう自分のソウル・ミュージックの旅の原点がスタックスだった。
モータウンがオシャレな箱と包装紙に包まれたチョコレートなら、スタックスはおじさんが新聞紙に包んでくれる焼きイモのようなソウルだ。持った途端にやけどするくらい熱い焼きイモだった。
そのスタックス・レコードの興亡を綴ったのがこの本「スタックス・レコード物語」だ。ページ数も多いのだが自分が好きなレコード会社の話なので丁寧に読んでいたらすごく時間がかかってしまった。最後の方、スタックスが倒産に向かっていくあたりはお金や裁判の話が多くてそういう話が嫌いな私にはちょっとつらかった。でも、スタックスが始まる頃の話は本当に自分がバンドを始める頃の話に似ていてウキウキする。みんなが素朴で純粋で、ただその音楽をやりたいという情熱だけで行動する姿は「青臭い」
ようだが、それなくして事は始まらないし進まない。読んでみると「家族」のようだったというスタックスのミュージシャンとスタッフたちの絆の強さが全盛期のスタックスのサウンドにはちゃんと現れている。ミュージシャンもレコード会社も同じように成功していき、新しい事に取り組みいいものを作ろうという意欲が山の頂上に向かってみんなを押し上げていくプロセスは読んでいても楽しい。どんな風にしてヒット曲や名曲が作られたのかという話も興味深い。またそれぞれのミュージシャンの個性や性格などもわかって面白かった。しかし、大成功して自分たちが想像もしなかったお金を得た後が何事も難しい。このスタックスの物語でもそのことが詳細に語られている。
ひとつのレコード会社の興亡の話というだけではなく、音楽に携わるミュージシャン、スタッフ、レコード会社にとって何が大切なのかということがこの本には書かれている。
読みごたえのある、ディープな素晴らしい一冊でした。
|